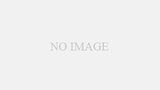今回は、トレンドの転換やエントリーのタイミング判定がしやすい「GMMA(複合型移動平均線)」の見方を解説いたします。GMMAは期間の異なる複数の移動平均線を短期群と長期群に分け、色分けして重ねて表示する指標です。用いるのは単純移動平均線ではなく、直近の株価に比重を置く平滑移動平均(EMA系)なので、株価の変化に比較的素早く反応します。

GMMAの全体像を見る際は、まず長期群(例:赤の帯)と短期群(例:青の帯)の“帯の向きと広がり(拡大・収縮)”に注目します。長期群が収縮から拡大へ転じる局面は、中長期の上昇トレンドが立ち上がる兆候です。そこに短期群の拡大が重なれば、上値は軽くなりやすく、トレンドが強い状態と判断できます。特に分かりやすい転換サインは、短期群(青の帯)が長期群(赤の帯)を上抜けて、その上で推移し始める場面です。これは中長期のトレンド転換を示しやすく、仕込みの起点になり得ます。その後、短期群が長期群の上で保たれる限り、上昇トレンドは継続しやすいと捉えます。
短期売買のタイミング取りでは、短期群(青の帯)とローソク足の関係を細かく見ます。株価が短期群の上で推移している間は、高値更新が続きやすいので基本はホールドです。押し目を狙うなら、株価が短期群の帯の中へ一旦入り込み、下限付近の移動平均線で下げ止まって反転する場面が候補になります。ここでしっかり反発し、ローソク足が短期群を再び上回ってくる動きが確認できれば、再上昇に乗りやすくなります。

一方で注意したいのは、株価が短期群(青)を明確に割り込むケースです。短期群を割ると、次の支持は長期群(赤)になりやすく、そこまでの下落リスクが高まります。短期的な下降転換の初期サインとしては、短期群の帯が“ねじれる(帯同士が交差して拡散する)”現象も挙げられます。このねじれは勢いの鈍化やトレンドの変調を示しやすく、戻り待ち・様子見に切り替える判断材料になります。
もっとも、短期が崩れても直ちに中長期まで崩れるとは限りません。長期群(赤の帯)は次の強い抵抗帯(支持帯)として機能しやすく、十分な下落の後で“最終押し目”になって切り返すこともあります。したがって、短期ではリスク管理を厳格に行いつつ、長期群付近での下げ止まり・反転の兆候が出るかを丁寧に見極めることが重要です。
今回はこのようなGMMAの見方とトレンド転換・タイミング判定を動画で解説していますので、ぜひご覧ください。